白龍亭・神女の玉配り
■ 目次 >> 考察 >> 八犬伝の謎/神女の玉配り(2025年 4月~)
[ 八犬伝の謎 - 17 ]
● 御指摘 from 伏姫屋敷様
地図「八犬士生誕地」ページで、伏姫自害時の八玉の飛散について触れた。
それに対して、八犬伝サイト「伏姫屋敷」の ゆーかさんから下記の言葉を頂いた。
* 当サイト内へのリンクは同タブ、他サイトへのリンクは別タブで開く。
「伏姫が手束に玉を投げ与える場面が強く印象に残っていて、この場面の挿絵で他にも玉らしいものを複数所持しているので、伏姫が各犬士の周辺に玉を配置して回ったイメージだったのですが、確かに考えてみれば伏姫切腹時に玉はいったん四散してるのですよね。それを伏姫自ら回収したうえで、また配り直している・・・なんか意味深です」
実を言うと、亭主は、伏姫神女が手束に玉を投げ与える場面をすっかり忘れていた。
この言葉を頂いて「そういえば、そうだった」と思い出したのである。亭主は元々記憶力が良い方ではないものの、長年八犬伝サイトを運営している人間が、これほど重要なシーンを忘れているとは! はっははは(自嘲)
* 余談。脳内で記憶を司る海馬が、感情を司る扁桃体の横にあるため、記憶は感情の影響を受ける。退屈だと記憶力は下がり、楽しかったり驚いたりすると記憶力は上がる。記憶力の良い人は、退屈でも学習に困らないレベルの記憶力を保持するが、亭主のように記憶力が悪い人間は、退屈な感情で学習すると壊滅的な結果にしかならない。こういう人間にとっては「いかに楽しく学習できるようにするか」が極めて重要な課題となる。
ま、それはともかくとして──
ゆーかさんの御指摘のとおり、「飛散したはずの八玉を、伏姫神女が配っている」というのは、かなり不思議な図式である。ということで、自分なりにあれこれ考えてみた。
● 瑞玉 from 伏姫神女 with 犬
まずは、該当箇所の引用から。
* 面倒なら、原作引用部分を読み飛ばしたり、斜め読みしても可。それでも理解できるような文章にしてある。
「時に長祿三年〔伏姫自殺の翌年なり。〕九月廿日あまりの事なるに、(中略)南のかたに靉靆と、紫の雲たな引て、地を去ること遠からず、と見れば嬋娟たる一個の山媛、楚の宋玉が夢に見えし、神女の俤をとゞめ、魏の曹植が筆を託せし、洛神の顏をうつして、黑白斑毛の老犬に尻うち掛、左手に數夥の珠を拿て、右手に手束を招きつゝ、辭はなくて一ッの珠を、投與給ふになん。手束は今この奇特を見て、おそるおそるついゐたるが、遽しく手をさし伸て、件の珠を受んとせしに、珠は手股を漏て、輾々と、雛狗のほとりに落しかば、其首か彼首かと索ても、索ても又あることなし。あな訝し、とばかりに、そなたの天をうち仰げば、靈雲忽地迹なくなりて、神女も共に見え給はず」
(第二輯第十六囘)
老犬にまたがった神女が、左手に複数の玉を持ち、右手で後に信乃を産む手束を手招きしつつ、無言で玉をひとつ投げた。
どう考えても、この神女は、八房に跨った伏姫以外にはありえないが、実のところ、この神女が伏姫だとはどこにも書かれてはいない。
手束が子宝を祈ったのは弁才天だから、神女が弁才天である可能性も否定はできない。かつて、伏姫が洲崎明神の役行者の石窟を参詣した帰路に、役行者と思われる名称不明の爺から八玉を含む数珠を授けられた。それと同じパターンだとすれば、弁才天の岩屋を参詣した帰路に出会って玉を授けてくる名称不明の神女が弁才天であってもおかしくはない。
だが、弁才天は犬にまたがったりしないし、瑞玉にも無縁だ。実際、神女を見た手束は「弁才天には見えなかった」と言っている。
手束「拜れ給ふ神女の姿は、山姫といふものめきて、辨才天に似給はず」
(第二輯第十六囘)
* ただし、あくまで「通常の」弁才天の姿ではない、というだけ。弁才天説を完全否定できるものではない。
* このテーマに関して、ゆーかさんの「伏姫屋敷」の本論に「伏姫は弁才天?」及び「伏姫は弁才天?(2)」という考察ページあり。
弁才天の話はこのページのテーマから外れるし、亭主に弁才天を語れるほど知識がないこともあり、これ以上は触れない。
* 余談。日本三大弁才天のうち、関東にあるのは江ノ島。江ノ島といえば龍神。北条時政が家紋を三つ鱗にしたのも、江ノ島参詣から龍の鱗に由来。で、里見氏の引両紋も、易の陽爻(⚊陽爻/⚋陰爻)に由来するとの説があるが、これもまた龍がらみ。全陽の卦=乾(䷀)の易経本文「乾、元亨利貞。初九、潜龍、勿用。九二、見龍在田。九三、君子終日乾乾、夕惕若。厲无咎。九四、或躍或淵。无咎。九五、飛龍在天。利見大人。上九、亢龍有悔。用九、見羣龍无首。吉」が龍づくし。ったく、何でもかんでも龍かよ。安直だな。……え、おまゆう?
↑第十六回の挿絵の部分模写。
本文を読んでも、柳川重信が描いた挿絵を見ても、確かに伏姫神女は、八方に飛散したはずの玉を手に持っている。
やはり、一旦飛散した玉を回収し、改めて配っている。玉を犬士に届ける上で、なんで、そういうややこしい手順を踏む必要があるのか?
* 余談。元の挿絵はなかなかに複雑で、ペンタブレットで模写しつつも細部は再現できなかった。それほどに複雑な原画って、版木に彫られて印刷したものだよなぁ。彫師すげぇ、と思った。
● The first 玉配り by 伏姫神女
手順云々を考える前に、気になったことがある。
挿絵に描かれた、玉の数だ。
伏姫神女の右手から放たれた「孝」の玉の他、左手に5つの玉が見える。ただ、手の形状から指に隠れた玉が1つあると思われ、左手に計6つの玉を持っている。投げた玉を含めて、この時点で伏姫神女が持っている玉は総計7つだ。
仁義礼智忠信孝悌、全部で8つの玉があるのだから、この時点で神女の手元に7つしかないとすれば、すでに配り終えた玉があることになる。
物語的にはこの場面が初の玉配りだが、時系列で見ると初ではない。
では、時系列で見た初配りは誰の玉か?
実はこの答は明白。犬山道節の「忠」の玉である。
道節「かくて阿是非は有身て、長祿三年九月戊戌の日に、男兒を産てけり。出生の子は則われなり。われ生ながらにして、左の肩尖に、大きやかなる瘤あり、その形松の癭に似たればとて、道松とぞ呼れたる」
(第三輯第廿八囘)
後の道節である道松は、生まれながらにして左肩に瘤がある。後々ここから玉が飛び出す、あの瘤だ。
つまり「忠」の玉は、長禄三年九月戊戌の日までには、配り終えている。問題は、この「九月戊戌の日」と、神女が手束に玉を投げた「九月廿日あまり」のどちらが先か、という事だ。調べてみると、九月戊戌の日は九月十九日。手束の場面より以前だ。
* カシオが運営している「高度計算サイト」で、和暦西暦変換と、干支カレンダーを組み合わせることで、日付が分かるのだ。ちなみに、長禄三年九月十九日は、1459年10月15日。
もっとも、馬琴が九月戊戌の正確な日付を理解した上で書いたのかは微妙だと思う。とはいえ、神女と手束の出会いを九月下旬に設定している時点で、こっちが後という意識をもって書いているような気もする。
* そもそも道節には玉の回収も玉配りもしていない可能性がある。詳細は後述。
なお、これを機会に、道節だけでなく、八犬士全員の玉入手を改めて確認してみた。
やはり、伏姫神女が姿を現したのは「孝」の玉の時だけ。
信乃だけが優遇されているように見えるが、これは「物語的に初配りだから」という理由だけであろうか。この部分も含めて考察したい。
● Twin 伏姫s
伏姫は二人いる(えっ?)
* いきなり極端な話から始めて読む人を引き付けた後、わりと凡庸な結論に導く。よくある竜頭蛇尾の手法。
八玉が飛散した時の伏姫と、玉配りをしている伏姫。この両者は、異なる伏姫なのだ。
つまり、前者の伏姫は人間、後者は神女。霊魂だけが継続して同一なだけで、能力を含めて、他は別個の存在だとすら思える。この断絶は、まるでサナギと蝶の関係に似ている。あるいは、変身や形態変化とも捉えられると思う。
| |
伏姫 |
八玉 |
| 第一形態 |
人間 |
数珠(+百の小玉) |
一連 |
文字変化あり |
| 第二形態 |
神女 |
各犬士の玉 |
個別 |
文字固定 |
| 第三形態 |
四天神像の目 |
二個一組 |
文字消滅 |
伏姫の形態変化を表にしてみた。
同時に八玉にも大きな変化があり、数珠を構成する部品のひとつに過ぎなかった八玉が、個別の存在として独立するのだ。
そもそも、この数珠は何だったのか。
「翁の爲體、凡人にはあらざりけり。(中略)「寔に靈の祟あり。これこの子の不幸なり。禳ふにかたきことはあらねど、禍福は糾る纏の如し。譬ば一個の子を失ふて、後に夥の翼を得ば、その禍は禍ならず。損益の方みなしかり。歡ぶべからず、哀しむべからず。まかり皈らばこのよしを、義實夫婦に告よかし。これまゐらせん、護身にせよ。思ひあはすることあるべし。」と誇㒵に説示し、仁義禮智、忠信孝悌の八字を彫なしたる、水晶の珠數一連を、懐よりとり出して、閃りと姫の衣領にかくれば、(中略)從者等は忙然と、霎時其方を見送りつ、これ全く役行者の、示現にこそ、と思ひとりて…」
(肇輯第八囘)
霊に祟られている伏姫の「護身用」に、役行者らしき爺からもらったものである。
となると、伏姫読経の功徳で、八房の内なる玉梓の怨霊が成仏した時点で、この数珠の目的は完了したのだ。数珠の文字が「仁義禮智、忠信孝悌」から、一時「如是畜生、發菩提心」に変わるというメッセージ機能が発動したが、それが完了の合図なのである。
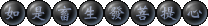
上の引用の役行者の言葉の中に「一個の子を失ふて」とある。
つまり伏姫が早くに死なねばならないのは定められた運命であり、数珠の護身という任務が完了した時をもって、次のステージ=八犬士誕生に進まざるをえない。ここで、伏姫も八玉も形態変化するのである。
次に、伏姫自害と八玉飛散の場面を引用する。
* これは「八犬士生誕地」でも引用しているので重複するが、重要な個所なので「別ページ参照」にはせず、改めて引用する。
「護身刀を引拔て、腹へぐさと突立て、眞一文字に掻切給へば、あやしむべし瘡口より、一朶の白氣閃き出、襟に掛させ給ひたる、彼水晶の珠數をつゝみて、虛空に升ると見えし、珠數は忽地弗と斷離れて、その一百は連ねしまゝに、地上へ戞と落とゞまり、空に遺れる八の珠は、粲然として光明をはなち、飛遶り入紊れて、赫奕たる光景は、流るゝ星に異ならず。(中略)八の靈光は、八方に散失て、跡は東の山の端に、夕月のみぞさし昇る。當是 數年の後、八犬士出現して、遂に里見の家に集合、萌芽をこゝにひらくなるべし。かくても姫は深痍に屈せず、飛去る靈光を見送りて、「歡しやわが腹に、物がましきはなかりけり。神の結びし腹帶も、疑ひも稍解たれば、心にかゝる雲もなし。浮世の月を見殘して、いそぐは西の天にこそ。導き給へ彌陀佛。」と唱もあへず、手も鞆も、鮮血に塗るゝ刃を拔捨、そがままに磤とふし給ふ。こゝろ言葉も女子には、似げなきまでに逞しき、㝡期は特にあはれなり」
(第二輯第十三囘)
ここで、八玉は一連の数珠という形態から、個別の玉に変わる。
それを見届けた上で、伏姫は人間としては死に、神女として再生する。
両者に微妙な時間差があるものの、ここが転換点であり、「八玉の飛散」と「伏姫神女の玉配り」との断層でもある。
● 八玉 with 白気 from 伏姫
第十三回で「八の靈光は、八方に散失て」とあるので、もしかして、霊光だけが八方に飛んで、八玉は見えなくなっただけで富山に留まったのでは?との疑念が浮かんだ。
しかし、その考えは、次の第十四回で打ち消された。
義實「伏姫が自殺の今果に痍口より、一道の白氣たな引、仁義八行の文字顯れたる、百八の珠閃き沖り、文字なき珠は地に堕て、その餘の八は光明をはなち、八方へ散亂して、遂に跡なくなりし事、其所以なくはあるべからず」
(第二輯第十四囘)
丶大「今より諸國を徧歴して、飛去たる八の珠の落たる所を索ねもとめ、はじめのごとく繋ぎとめんに、一百八の數に滿ずは、又當國へ立かへりて、見參に入り候はじ」
(第二輯第十四囘)
一部始終を見ていた義実や丶大が、明確に「玉が八方に散った」という認識を持っているし、丶大は「玉が落ちたところを探す」と言っている。
つまり、伏姫神女は、玉配りの前に散った玉を回収したことが確定。
まず、なぜ「回収したのか?」以前に、「なぜ飛散したのか?」を考える。
玉が飛散した時、伏姫はまだ人間。つまり、玉を操る能力はない。
となると飛散時には、玉はまだ役行者の管轄下にあった。そもそも運命を定めるのは天であって、役行者は単に天機あるいは天命を知る者にすぎない。だが、天命の執行者として、その場にいて影ながら玉を飛散させたか、時が来たら玉に飛散するプログラムを事前に施したか、いずれにせよ司っているのは役行者であろう。
役行者ほどの存在が、無意味に玉を飛散させるだろうか? 否。
ここで重要なのが、伏姫の切腹傷から出てきた「一朶の白氣」あるいは「一道の白氣」だ。
これは八犬士の種子。
丶大も後に、白気→八犬士である語っている。
丶大「汝達は、おのおの父あり母あれども、その前身は伏姫の胎内より顯れ走りし、白氣の生れるものなるか。その因を推して果をおもへば、皆伏姫のおん子にして、義實朝臣の外孫たるべし」
(第四輯第三十七囘)
この白気が玉を包んだ時に玉は光った。そして光は飛散した。
つまり、飛散したのは玉だけではなく、八犬士の種子も飛んだ。であるならば、玉の飛散は、この種子を生誕地に運ぶのが主目的と考えられる。
では、なぜ伏姫が神女になってから玉だけ回収したのか?
ここは発想を逆にして、仮に全く回収されなかった場合を考えてみる。
実は玉を回収されていない可能性がある犬士がひとりだけいる。犬山道節だ。
前述では、手束より以前に神女が玉を配ったと考えたが、そもそも「忠」の玉は回収していない可能性だって考えられる。なぜなら、道節は生まれながらに体内に玉を持っていたから。
* 親兵衛も生まれながらに玉を持っていたが、彼の場合は手に握っていただけで、体内ではない。つまり、玉を内蔵して生まれてきたのは道節ただ一人。
* ただ、親兵衛の場合、母である沼藺が光っていた玉を飲み込んでいる。この時に親兵衛の種子をいっしょに取り込んだのであろう。となると、これまた未回収の可能性もでてくる。ただ、これは伏姫神女が手束に玉を投げたのより、かなり後の話なので、種子と玉がセットになっていたとしても、一度回収して機を見て配り直した可能性が高い気もする。
神女の玉配りが無く、玉の回収がなかった場合、八犬士全員が生まれながらに体内に玉を持つであろう。
何らかのイベントで体外に出るのは必定だし、その時に文字の入った水晶玉などという珍奇なものを目にすれば、特別な物だという認識には至るであろう。ただ、それが伏姫由来だという話を聞かされた時、素直に納得できる材料がない。
たとえば、道節が荘助から玉の因縁を聞いたシーン。
莊介「長祿二年の秋、伏姫富山に自殺の折、その除數の八の玉は、一道の白氣と共に、八方へ散亂せしよし、近會同因の兩三友、下總の行德にて、里見の舊臣、金碗入道丶大坊、密使蜑崎十一郎等に邂逅して、その來歴を定かに知れり」
(第五輯第四十七囘)
荘助から伏姫因縁を聞いて、道節も話を信じる。
それは、痣と玉を見て荘助との間に運命的な関係を確認したからだ。
前段階として、荘助も、信乃・現八・小文吾から伏姫由来の物語を聞いて受け入れている。
さらに前の段階として、信乃・現八・小文吾が、古那屋で丶大法師から伏姫の話を聞いた時が重要な起点となる。ここで母・手束が伏姫神女から玉を授けられたという話を聞いている信乃がいなかった場合、そんな異国との因縁があると言われても納得できず、安房里見家で起きた突拍子もない話を信じない可能性もある。行徳あたりの栄えた場所からすれば、「安房? なんで俺がそんな辺境に行かなきゃならねぇんだよ」とか思って終わるだろう。
* 安房よりも辺境に育った大角はどう思うかわからないが。
つまり、八犬士全員が伏姫との因縁を受け入れるためには、八人のうち、少なくとも一人は伏姫との因縁を納得できるだけの経験をしていなければならない。
言い換えれば、少なくとも一人の犬士周辺で、伏姫神女が姿を現して玉を授ける必要がある。
であるから、丶大が最初に出会う犬士=小文吾、信乃、現八の誰かがそれを経験していないといけないわけだが、その宿命が信乃にあったということだ。
伏姫神女が自ら玉を配らなければならない理由はこれに尽きる。
● Return of 八玉 to 伏姫
ここで、配る前に必須の回収について考える。
前述の配布理由からすれば、信乃の玉だけ回収して、手束に配って終わりにすればよい。……と思える。
だが、他の七人が全員生まれながらにして玉を内蔵していて、信乃だけ神女授与だった場合、他の七人から見て信乃だけ偽物に見えるだろう。
神女が姿を現したか否かが、1:7であっても、犬士側が1:7を意識してはいけないのだ。不自然さを感じさせないためには玉の入手パターンに多数派と少数派の分断があってはならず、そのために各人がすべて異なるパターンで玉を得る必要がある。
その意味で、伏姫神女は全員の玉を回収して再配布しなければならない。
* 道節だけは回収の必要はなかったかも。
どうやって回収したか?
考えられるパターンは二つある。
① 伏姫神女が玉と子の種子が落ちた場所=生誕地に出向いて拾う。
絵面としては少々マヌケな感じだが、伏姫神女が自分の子供たちが生まれ育つ環境を下見すると思えば不自然ではない。現地を見て、どうやって配るかを考える材料にもなろう。……もっとも、手束の場面で「靈雲忽地迹なくなりて、神女も共に見え給はず」という神出鬼没ぶりを見せているぐらいだから、距離という空間的制約なしに移動可能。現地に出向いたとしても、それは「わざわざ」という副詞をつけるものではなかろう。
② 八犬士の種子を生誕地に送り届けた玉が、神女となった伏姫の下に帰還する。
飛散が自動的に遂行されたのだから、天の意志に従う玉が、人間から神女へと昇格した伏姫のところに、自動的に戻ってくるのが自然であろう。
* この段階で、玉の担当者が役行者から伏姫神女に変わっているが、担当の引継ぎも、神仙同士ならば言葉もいらぬのであろうな。
どちらのパターンなのか検証に必要な材料がないので、これは答が出ない。
● Truth of 伏姫
伏姫神女が手束に投げた「孝」の玉は、結局、与四郎犬の体内に入ってしまう。
手束の手に渡らないのは、神女の意志というより、天の定めであろう。信乃が与四郎犬の首を斬るまで、信乃は玉を手に出来ない。そういう宿命を、神女といえども、変えることはできまい。
ただ、神女に玉を授けられたという事実が、手束を通して信乃に伝わるのみ。
これ以外にも、一旦他の生命の中に取り込まれて、その後で犬士本人に玉が渡る例が多い。
Ⓐ 仁・沼藺が飲み込んだものが、息子親兵衛の手の中に。
Ⓑ 礼・雛衣が飲み込んでしまい、雛衣自害と共に角太郎の手に戻る。
Ⓒ 信・調理した魚の腹から玉が出てきた。
Ⓓ 孝・与四郎犬が飲み込んだ?が、斬首とともに玉が信乃に飛んできた。
玉を取り込んでしまった犬士以外の生命は、結局は、玉の出現と引き換えに死ななければならない運命。
天意とは残酷である。
* 魚は、玉に関係なくても食われていただろうけど。
伏姫が神女となって、里見家は八犬士とともに栄える。
とはいえ、里見家は四代目以降乱れに乱れるし、二世犬士はただの人間。神女由来の栄華は一時の夢でしかない。虚しい話だ。
……と最初は思ったけど、案外、神女の思いどおりになったのかも。
伏姫の不幸は怨霊に由来する。
だが、玉梓を怨霊にさせたのは、父・義実と金碗八郎だ。伏姫にしてみれば「なんで親のせいで自分が不幸にならなきゃいけないの?」という不条理への怒りはあろう。てことは、弟・義成以降の里見家がどうなろうが知ったことではない。
伏姫にとって重要なのは、自分の霊的な子供たち=八犬士の幸福だ。
初代八犬士の幸福は里見家の栄華と連動しているから、神女は里見家を助ける。だが、孫たる二世犬士の幸福は、四代目以降に乱れる里見家から離れることにある。だからこそ、初代犬士をして二世犬士に里見家を見捨てるよう促したのだ。
* 結局、八犬士には里見家への忠義などなかったわけだ。
で、ここまで考えて気づいた。
八房が成仏した時、八玉の文字が「如是畜生發菩提心」に変わったが、これは「犬畜生でも菩提の心を発した=成仏した」の意味。その後は言葉にないけど、暗に「まして人間なら当然成仏する」と皆思う。つまり伏姫も成仏したと。それで神女になったと。
もしかして、違うんじゃないの?
犬畜生すら成仏したけど、人間は成仏していないかもしれないのだ。
伏姫に「なんで親のせいで自分が不幸にならなきゃいけないの?」という思いがあったとすれば、そういう煩悩を昇華させず残したままでは成仏できまい。死後、「神女」を騙っている(あるいは、人間側がそう見ているだけ?)が、実は「怨霊」になったのかもしれない。
* それもまた天意なのだろう。
そう考えると、二つの謎が解ける。
ひとつは、神女を見た手束が「山姫といふものめきて、辨才天に似給はず」と言った事。
一般に山姫とは妖怪の類だ。そんな姿に見えたのが不思議に思っていたが、実は怨霊なのだと考えれば、手束の素直な感想こそが真実に迫っていたのだ。
もうひとつは──
濱路姫「いと嬋娟なる一個の神女、最大きなる狗兒の背に、尻うち掛つゝ忽然と、虗空より降り來まして、女僧を遮留め給へば、女僧は怕れし面色にて、斫拂ん、と角ひもあへず、神女に胸を撲地と蹴られて、奴家を捐て仆れ侍り」
(九輯中帙第百十四囘)
──浜路姫を救うために、妙椿尼の胸にキックをかました姿だ。
いかに神女を騙って「良い子ちゃん」をやっていても、ついつい出てしまう暴力的本性。怨霊っぽいよね。
* 神女という建前上の伏姫を継ぐのが、犬江親兵衛。だから、神薬と称する怪しい薬で死者を蘇らせたりする。一方で、怨霊の本性を継ぐ犬士が、犬阪毛野。洲崎沖水戦における皆殺しの作戦は、とても仁慈などではない。
* 伏姫の暴力性に関して、ゆーかさんの「伏姫屋敷」の勘ぐりと細かいネタの項目下に「バイオレンス伏姫」と「スプラッタ伏姫」及び「「けころす」伏姫」という考察ページあり。亭主はすっかり忘れていたが、上記の場面以外にも、暴力性を示すシーンがあったのね。ご教示下さり感謝。
玉配りについて考察するつもりが、伏姫の裏の顔が見えてしまったよ。
* このページは「八犬伝の謎」の項目で書き始めたけど、結末だけ見れば「八犬伝邪読」の項目下におくべきだったかも。